ずいぶんと、記事の投稿をおさぼりしてしまった。ありがたいことに、徘徊アカデミアの紹介記事を、とある学術雑誌に書かないかとお声がけいただいた。2021年の秋のことだ。しかし、私の力がまったくおよばず、ウェブサイトの世界観や、執筆者のそれぞれがアカデミアとのほどよい距離感を模索しようとしている様子など、うまく文字化できないまま今に至っている。
さまざまなツールを使って発信ができるようになるなかで、研究をアピールするために、TwitterなどのSNSだけでなく、ブログやホームページを活用する研究者の方々がたくさんいる。徘徊アカデミアはというと、あまり自分のことをアピールするのは得意ではないけれども、しまっておくには忍びない経験を、どうにか形にできればという思いから始めたものだった。研究ジャーナルの、しかも新たな挑戦のようなコーナーに紹介していただくのに、ふさわしいものではなかったかもしれない。
いったん引き取って私が下書きをし、徘徊アカデミアの執筆者の皆さんにみてもらったうえで、編集委員の先生に提出した。その後、編集委員の先生からは、それぞれが何の研究をやっていて、結局のところ何を明らかにしたのか、何を主張したいのかが、とんと伝わってこないという趣旨の、丁寧なコメントをいただいた。時間を割いて読み、コメントをくださった先生には感謝しかなく、言わんとしていることは理解できる。しかし、コメントに応えることがなかなかに難しいとも感じている。宙に浮いたままの紹介文を、なんとか成仏させたい。そこで、徘徊アカデミアに、徘徊アカデミアの紹介文を載せてしまおうと思う。
脱力してアカデミアを徘徊する(2021年12月執筆、文責:西直美)
アカデミアでやっていくには、よくも悪くも人のあいだで噂にのぼり続けなくてはならない。学会など、つながりを構築する場に積極的に出かけていき、声を大きくして、私はここにいると売り込んでいかなくてはならない。そうでなければ、死んでいるのと同じだと叱咤激励を受けることがしばしばあった。筆者の場合、たいてい力が抜けているし、発表はスマートにできず、論文の形にするのにも時間がかかる。競争に勝ち抜いてきた自負がある先輩方にいわせると、社会をなめている人間のようだ。
大学院を修了しポスドクと呼ばれる身分になってから、アカデミアで「やらねばならない」とされていることがそれほど得意でない、あるいはマイペースにやっている人たちもいることに気がつくようになった。ポスドクやノラ博士は、所属や収入という面では不安定で、創作童話「博士が100人いる村」ではおよそ1割が行方不明になっているなど、悲哀ばかりが語られる1。そのようななか、世界を徘徊しながら気づいたこと、考えたことを、ひっそりと発信していく場があってもよいのではという思いから立ち上げられたのが徘徊アカデミアだった。できたばかりの「〇〇」(注:名称は伏)に、さっそく水を差してしまいそうなほどテンションは低めである。「ひっそり」が身上の徘徊アカデミアではあるが、このようなノラ博士もいるのだということが、どこかで誰かの糧になればという思いで筆をとっている。
徘徊アカデミアという場
ウェブサイトを一から構築し、記事をあげ始めたのは、新型コロナウイルス感染症の拡大が顕著になった2020年の4月である2。徘徊アカデミアは、たまたまご縁があったノラ博士の、さらにまたご縁が広がるかたちで続けられてきた。研究分野が異なる人がゆるやかに集まっているだけで、とくに決まりごとはない。何かあるとすれば、自分のなかにしまっておくだけではもったいない記憶や経験を、文字のかたちにするということである。
随時、執筆してくださる方を募集しているものの、いまのところ執筆者は海外の、さらにいえば(たまたまアジアに集中しているが)ニッチな地域やテーマについて調査を行ってきた人が多い。2020年4月以降、ペースを設定するため週に1回、フィールドワークの四方山話を中心に日本番外編3、読書メモ4などをあげてきた。2021年10月以降は、第2、第4土曜日の2回記事の更新を行っている(注:2022年2月以降は、編集担当が息切れしたために休憩中)。
大学院生の皆さんのように、移動が制限されたことで学位取得に向けた計画が狂ってしまうということはなかった。しかし生活や研究を含めて、さまざまな側面で影響を受けたのはノラ博士も同様である。社会が大きく変化していくなかで、「コロナ以前」のフィールドでの経験を書くことは、自分自身と向き合う作業ともなった。徘徊アカデミアに投稿された一つひとつの記事が、それぞれの執筆者の世界や人間との向き合い方を表しているようで面白い。
ノラ博士が切り取る世界
ノラ博士によって切り取られた世界を、ほんの少しだけ紹介してみたい。
中屋昌子「普段通りにしようとするな」(徘徊アカデミア2020年7月25日)
“相手のどんな些細ないいところを見つけて、それを相手に言う。そして、言われた側は、その褒め言葉を素直に喜ぶ。これって、現代社会に必要な特効薬なのかもしれません。どんな情況においても。「自助努力」だけでは、生きてゆけません。心のビタミンが必要なのです。…夜の帳が下りる頃。夕暮れの海を眺めながら、ゆっくりと時が過ぎてゆきます。チャイの杯を重ねながら、友人とのおしゃべりもまだまだ続きます。”
歴史や政治に翻弄されるウイグルの人々に寄り添ってきた中屋が描きだすのは、世界のどこかで、たしかに生きてきた人々の姿だ。パンデミックはフィールドへ行くことを難しくした半面、混乱のなかで救ってくれたのもまた、フィールドから得られた知恵や友人であった。
井上航「よく噛んで味わう」(徘徊アカデミア2020年9月12日)。
“「こりんこりん」にはやられた。外の音だったものが、ふとしたことで身体のリズムに入りたがり、わたしの聴覚・触覚・味覚が「こりんこりん」したい、となるのだ。似姿をもとめること、模倣すること、すなわちミメーシスのいとなみから、精霊がうまれる。身体に何かがおこる。精霊におどらされ、ワタシがむしろそらごとだと知らされ、ときを味わわせてもらうのだ。「こりんこりん」はよい霊だ。よく噛んでいこう。”
井上は、カンボジアの、ラオスやベトナムの国境に近い地域にあるクルンの村で調査を行ってきた。アニミズムを体現する民族音楽に向き合うなかで培われてきた独特のリズム感覚で、文字のひとつひとつが、そして文章の全体がまるで詩のようだ。
樋口雄哉「夜のイスティクラル通り(前編)」(徘徊アカデミア2020年12月12日)
“こうしたちぐはぐさのひとつひとつが、店全体がひとつの罠であることのサインであるように思えてぞっとした。魚が目の前の餌からテグスが伸びているのに気づくときとか、旅人が光に引き寄せられて入った山中の荒屋で若い娘のお尻からキツネの尻尾が出ているのを見てしまったときとかも、こういう鋭い恐怖を感じるのだろうと思う。”
フランス哲学を研究する樋口が書くのは「研究のついでにした寄り道や脱線、研究から逃避して行った遊び」である。樋口が徘徊するノワールな世界は、人間の存在について徹底的に考え抜いてきた哲学者ならではのバランス感覚で、露悪的になることがない。
山本文子「2桁当てオヤジ」(徘徊アカデミア2021年5月8日)。
“純粋な仏教とはどこか違う、仙人っぽいけれども、どこか胡散臭さもぬぐえないような、といういろんな思いが「ボードー」という言葉には込められているのだ。このボードーも、瞑想によって得られた第六感を違法くじに応用して「2桁」をバンバン当てまくっており、そうかと思えばそのお金を社会に還元していた。良いとか悪いとかでは切り分けられない曖昧な領域がそこにはあった。”
ミャンマーにおける霊媒の世界の探究からはじまった山本は、「人間くさい」人たちを軽妙なタッチで描写することを得意としている。紆余曲折を経て山本は、いまやミャンマー映画とヒップホップを語ることができる日本で唯一の人材となった。
「3つ目のハリラヤ」(徘徊アカデミア2021年1月9日)
“地域の知識人(ずいぶんな変わり者として知られていた)は、ここは発展していない地域で、仕事もしていない人が多い。ゆっくりとした生活ができるからこそ、このような行事がまだできているのだ、と私に言った。”
筆者は、何が専門なのか自分でもよくわからないが、イスラームをめぐる価値観の違いに関心があって勉強を続けている。徘徊アカデミアでは、タイ南部国境県の人々の日々の暮らしや、イスラームの信仰について比較的真面目に書いてきた。
「夏の日の2020年-そうだ、日本へ行こう-」(徘徊アカデミア2020年9月5日)
“小生も他の日本人教員と「今年は日本に行くの、無理だよね」と言い合っていた。それでも7月に入り日本行きへの執着はくすぶり続けた。一か八かの精神で学科の上司に「日本へ行ってもいいですか」と尋ねてみた。意外にもその回答は、「行けばいいじゃない。誰が行くなと言ったの?」である。今年一番の衝撃であった。”
安田は日本でのポスドク期を経て、海外に活路を見出して日本を飛び出していった人物である。海外で教えるということ、そして海外(おもに韓国)との行き来をめぐる体験を共有してくれる。
おわりに
生きている間に論文などを量産して評価されることを目指すでもなく、生きている間は日の目をみなくてもよいと脱俗遁世を決め込むというのでもなく、いまここで何かを発信する場があることにも意味があると考えている。パンデミックによって、社会にすでに存在していたひずみがあらわになった。めまぐるしく変わる世の中だからこそ、自分がしてきた経験や、その経験から得られた知恵が一筋の光となることもあるのではないだろうか。今後も、記憶の断片を形として残すことができる場を、ひっそりと続けられたらと思っている。しまっておくのにはもったいない話がある方は、ぜひともご参加いただきたい。
- 大学院修了者たちの困難な状況を描き、社会に衝撃を与えたのが、水月昭道『高学歴ワーキングプア「フリーター生産工場」としての大学院』(光文社新書、2007)だった。本書で水月は、30歳を過ぎて就職口のない博士たちを「ノラ博士」と呼んでいる。ノラ博士は、非常勤講師をしながら本業の研究・教育を続けるが非常勤の給与が安いために、ワーキングプアにならざるを得ない。本文中に引用した「博士が100人いる村」は、平成12年度版学校基本調査に基づいて創作されたといわれている。この創作童話では、100名のうち8名がまるで死亡しているように描かれているが、必ずしもそうではないことには注意が必要だろう。ノラ博士という言葉はネガティブな意味で使われることもあるが、当事者によっては大学や組織から自由であるというポジティブな意味合いを込めて使われることもある。近年では、大学などに見切りをつけた博士が、「在野研究者」として新たな方向性を模索している様子もみられる。
- まったくの素人である管理者がゼロからウェブサイトを構築してきた様子は、以下に記録している。もし自分でウェブサイトを作ってみようと思う方がいれば、他山の石となれば本望である。https://haikai-academia.com/category/websitebuilding/
- コロナでフィールドには行けなくなったことで、身近な場により目が向くようになった。日本番外編は、執筆者らが「その辺」を徘徊した所感を収録している。
- フィールドの四方山話ばかりでなく、読んだ本などの備忘録的な記事を載せる場があってもよいのではないかということで作られたコーナーである。

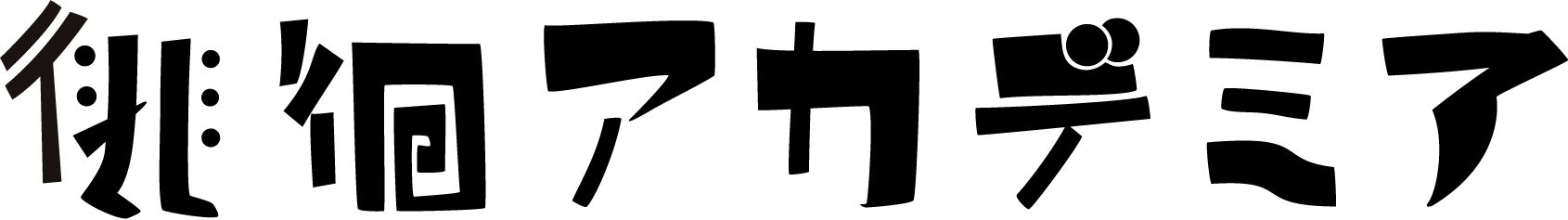






コメントを残す